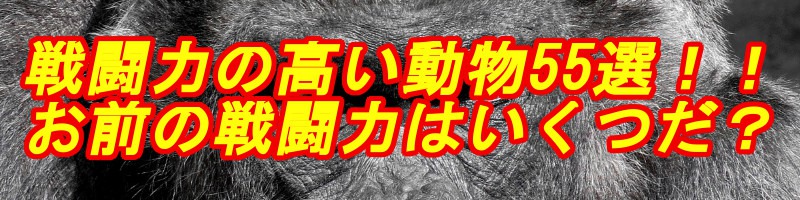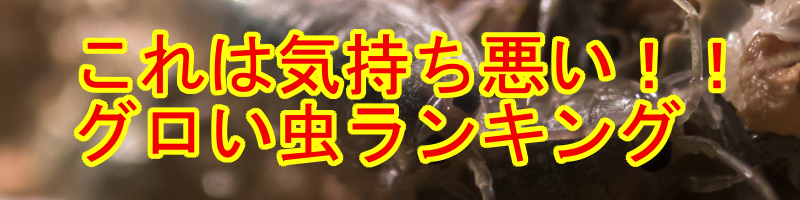砂浜には様々な貝の殻が打ち上げられていますが、日本沿岸だけでも数え切れない種類の貝類が棲息しており、貝殻だけで種類を言い当てるなんてことは研究者でもないかぎり至難の技です。
海の近くで小さな法螺貝のような生き物がいたら、それはもしかしたら「イボニシ」かもしれません。
今回は、食用貝としてもポピュラーなイボニシについて、みなさんにご紹介していきます。
イボニシってどんな生き物?
イボニシは、吸腔目アッキガイ科に属する巻貝の一種です。
最大でも殻長5.0cm程度と小さいながらも、その貝殻はサザエや法螺貝のようにゴツゴツとしています。
イボニシは漢字で「疣螺」と表し、「疣」は小突起、「螺」は巻貝を意味します。
「小さな突起のある巻貝」を意味するネーミングは、巻貝らしからぬ“ひねり”のなさです。
カラシ、ニガニシ、タバコニシなど、地域によって様々な名で呼ばれており、その数はなんと100を超えます。
イボニシの生態
イボニシは北海道南部から九州まで日本全域に生息しており、国外ではロシア極東部や朝鮮半島、中国沿岸部からマレー半島まで極東アジアから東南アジアの海岸付近に広く分布しています。
干潟や砂浜の他に、岸壁や河口など様々な場所で見ることができます。
イボニシは完全な肉食性で、牡蠣やフジツボなど岩に固着する貝類を捕食します。
貝であるイボニシが同じ貝の仲間をどうやって食べるのかというと、イボニシは穿孔腺という器官から酸を分泌することで、獲物の貝殻に穴を穿つことができます。
その穴から貝の中身を食べることもあれば、貝殻の合わせ目から毒を注入して殻をこじ開け、中に侵入することもあります。
イボニシと人間との関わり
前述したように、イボニシは牡蠣を好んで捕食するため、牡蠣の養殖業においては害貝として広く知られています。
また、アッキガイの仲間には鰓下腺という器官から分泌される「プルプラ」という成分を化学反応させることで深い紫色を呈する性質があり、古くから染料として利用されてきました。
黄色の分泌液を日光に晒すことで赤みがかった深い紫色に変色し、その色は「貝紫色」または「古代紫」と呼ばれます。
食材としてのイボニシ
イボニシは分布域が広く、また採取が容易であるため、日本各地で食用されています。
生食には向いておらず、基本的には塩茹でや煮付けとして食されますが、大分県宇佐市などでは味噌汁の具として用いられることもあります。
内蔵には独特の苦味と辛味があり、珍味として酒の肴などにされることが多いそうです。
イボニシの仲間
イボニシと同じアッキガイ科の仲間に、レイシガイやアワビモドキなどがあります。
レイシガイはイボニシと同じくアッキガイ科レイシガイ属に属する近縁種で、山形県と大分県で局所的に食べられている食用貝です。
良い出汁が取れることから味噌汁に使われることが多く、また甘辛煮やかき揚げとして食べても非常に美味しいそうです。
殻長6.0cm前後とイボニシと比べて大きいため、より食べ甲斐があるといえます。
アワビモドキはアッキガイ科Concholepas属に属しています。
チリやペルーなど南米を原産とする巻貝で、冷凍輸入されたものが加工品として広く出回っていました。
見た目は似ているもののミミガイ科に属するアワビとは分類学的に遠い種であるため、アワビモドキという表記は誤解を招くとして、近年では「チリアワビ」や「ロコガイ」と呼ばれることが多くなっています。アワビに比べると風味は格段に劣ります。
日本では古来より貝類を好んで食してきました。
浅瀬や岩礁でイボニシを見つけたら、食べてみては如何でしょうか。
ただし、貝の仲間には有毒物質を蓄積しているものもあるので注意が必要です。
(ライター:國谷正明)
■ 海辺にいるゴキブリみたいな気持ち悪い虫「フナムシ」って害がある?
■ 砂浜や浅瀬で見かけるザリガニやエビみたいな白い生き物「スナモグリ」て知ってる?
■ 砂浜で見かける小さい白いカニ「ミナミスナガニ」って知ってる?