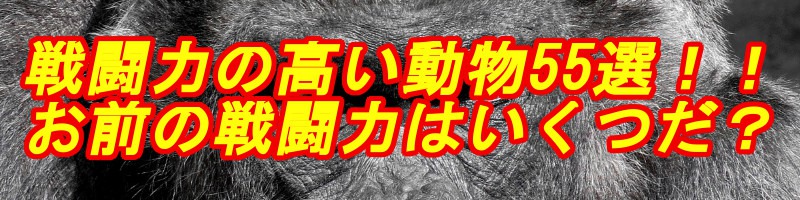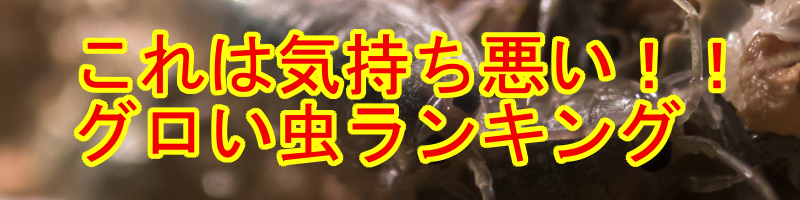砂浜や浅瀬で遊んでいると、小さなザリガニやエビに似た白い生き物を見たことがありませんか?
まぁ大抵のエビの仲間は見た目がそう違わないので、一括りに「あ、あれはエビ」だな、で終わってしまうかもしれませんが。
砂の中から出てきた小さな白いエビ、それは「スナモグリ」です。
今回はそんなスナモグリについて紹介していきたいと思います。
スナモグリってどんな生き物?
スナモグリは北海道から九州にかけて広く生息している、エビの仲間です。
大きさは5cmほどと小さめで、透き通るような白い体、そして片方だけ著しく大きなハサミが特徴。
なんでこんなにアンバランスなんでしょうかね。
真っ白なので弱々しくみえますが、意外に力は強く、このハサミに挟まれたらけっこう痛いんだそうです。
見かけても不用意に手は出さず、捕まえるにしても十分に注意してくださいね。
干潟に30cmほどの穴を掘って暮らしているので、干潟で気になる穴を見つけたらよく観察してみましょう。
捕まえようと思うなら、穴の周辺を深く掘ってみるのが一番手っ取り早いそうです。
一匹スナモグリを捕まえたら、次の穴にはそのスナモグリのお尻を突っ込んで、侵入者を排除しようとして出てきたところを捕まえるという上級者向けの方法もあります。
しかし捕まえるタイミングなどが難しそうですね。
釣り餌としてのスナモグリ
実はスナモグリについていろいろ調べてみると、生き物としての情報よりも釣り餌としての情報がわんさか。
正直、生態だのなんだのについては上に書いた程度の超薄っぺらい情報しか得ることができませんでした。
というわけで、釣り餌としてのスナモグリの情報をまとめてみます。
釣りが趣味だという人はすでにご存知かもしれませんが、スナモグリは「ボケ」と呼ばれていて釣り餌としてはとてもメジャーなんです。
(それにしても、誰がボケなんて酷い名前を付けたんだろう…。)
餌としては非常に優秀で、チヌ(クロダイ)、スズキなどの大物狙いや、カレイ、ヒラメなどの釣り餌としても使われます。
とても魚の食いつきが良いので、釣り餌として重宝している人は多いそうです。
しかし、そんな優秀なスナモグリにもデメリットが。
それは身が柔らかく、投げる際に千切れてしまったり、餌だけ食いちぎって行かれたりするケースが多いことです。
針の刺し方をきちんとしていなければ、魚が釣れる前に大量のスナモグリを消費してしまうことにもなりかねません。
スナモグリは釣り餌としては高価なので(大きさや地域にもよりますが、一匹20円~50円はします。)、無駄遣いをしないようにしなくてはいけませんね。
更に、スナモグリはとても生命力が弱いというデメリットもあります。
買ってから(捕まえてから)釣り場に着く前に死んでしまっていることもしばしば。
スナモグリは死んでもなお魚の食いつきは良いと言われていますが、それでも生きた状態にはかないません。
持ち運ぶ際には温度などに気を付けて、少しでもスナモグリが快適でいられるようにしてあげましょう。
スナモグリって食べられる?
エビやシャコに似ているので、食べたら美味しそうな感じがしますね。
しかし、スナモグリは食べることができません。
いや、食べても問題は無いんですが、美味しくないんです。
釣り餌として以外は市場に出回っているのを見たことは無いので、なんとなく想像はついていましたが…。
実際に食べてみた人の感想では、苦みがありとても泥臭くてまずかったそうです。
ちょっと残念ですね。
スナモグリ まとめ
釣り餌としてのスナモグリは高いから、自分で捕まえたものを飼育して増やせたら…なんて考える人もいるかもしれませんが、あまりお勧めはできません。
上にも書いたように、スナモグリはとても生命力が弱い生き物ですので、一般人が家で飼育しようと思ってもすぐに死んでしまう可能性大です。
釣り餌を売っているお店でも長期の飼育は難しいようなので。
釣り餌に使いたい場合は素直にお店で買うか、自分で干潟で捕まえてみましょう。
(ライター名 もんぷち)
■ 海辺にいるゴキブリみたいな気持ち悪い虫「フナムシ」って害がある?
■ 砂浜で見かける小さい白いカニ「ミナミスナガニ」って知ってる?
■ 砂浜や浅瀬で見かけるカタツムリみたいな貝「ツメタガイ」て知ってる?